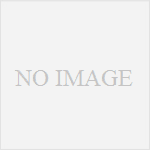「わたしのこと忘れないでほしい。」
忘れられること。自分がすべての人の記憶から忘れ去られる日がいつかはやってくる。自分が死んで30年後?、50年後?
こんなことをふと思ってしまったのは、バッハを聴いていた時だった。バッハは偉大な人で今でも人々に覚えられている。わたしはバッハがうらやましくなってきた。しかし、次の瞬間、うらやましいと思ったその次の瞬間には「そうでもないか」と気を取り直した。なぜなら、バッハだっていつかは人々から忘れ去られるからだ。
時間というものに思いを馳せるとき、どうしてもわたしは宇宙の時間を考えてしまう。そして、それを考えるとき、人間がまるで砂粒のような、瞬きのようなそんな感覚に襲われるのだ。
宇宙が誕生してから100億年以上はゆうに経っているらしいけれど、その最初から現在までに一体どれだけの人々が生まれては死んでいったことだろう。そして、その膨大な人間たちの数々の生涯には一体どれほどの意味があったのだろう。そんなことをわたしは考えてしまう。
みんな一生懸命生きたのだろう。石器時代の人々は彼らなりに毎日獲物をつかまえたり、木の実をとることに大忙しだった。そして、生まれては死んでいき、生まれては死んでいき、を繰り返して現在2022年の4月。かなり端折ったけれど、いつの時代にも人々は懸命に生きていた。が、その中で今でも人々の記憶に残っている人というのは何人くらいいるのだろう。
自分自身に問い返すなら、何でそんなに誰かの記憶にあることにこだわるのだろう、と不思議にさえ思う。まるでそれではインスタ映えを狙っている人たちと対して変わらないじゃないの。記憶に残ることがそんなに大切でそんなに大事なの? 記憶に残ったかどうかじゃなくて、今生きている一瞬に熱い火花をほとばしらせたかどうかの方が大事なんじゃないの?
人間って線香花火みたいなものだと思うな。それはそれは美しい線香花火。でも、それだとみんな寂しいから、その線香花火の火花を少しでも長持ちさせようとする。
わたしも文筆活動をしながら、何のために書いているのだろう、と自分に問いかける時がある。書きたいから書くのさ、と以前には答えたように思うけれど、それ以外にも本当のところは自分が生きた証を残したいという気持ちもあるんじゃないか、という気がしてきた。
生きた証か。何だか切ない話になってくるな。わたしは思うんだけど、何をやっても生きた証は残らないよ。どっちみち遅かれ早かれ忘れられる運命は待っているんだからさ。でも、そう言い切ってしまうと寂しいので、短い間だったら有効な証は残ると思うよ、と訂正しておきたい。わたしのことを知っている人、覚えてくれている人が死んだとき、わたしの生きた証も消えるんだ。そして、発掘されることがまれにあるとはしても、そうでもない限り忘却の彼方に完全に追いやられる。
そんな悲観的な話を逆転させるようなことがあるとしたら、それはキリスト教でいうところの最後の審判であり、復活であり、天国への希望だと思う。今までの話はすべて無神論的な考えが正しかった場合のことで、キリスト教の希望が実現すれば、そこでどんでん返しが起こるのである。
こうなったらもう「わたしのこと忘れないで」とか何とかは全部吹き飛んでしまう。だって、もう天国では永遠に生き続けるからだ。忘れないでも何もなくなるのは明らかだろう。
天国という場所がどのようなところで、どのような生活が待っているかということは聖書にも詳しくは書かれていないけれど、それでもまぁ、お楽しみといったところでわたし自身、とても楽しみにしている。天国の住まいって5DKくらいですか?、とか野暮なことは聞くまでもない。とにかく神様は快適なところを天国に用意してくださるだろうから、安心して赴こうではないか。わたしが思うには、現在の全宇宙と同じかそれ以上の広さ(?)を用意してくださるだろうな。そして、楽しい天国ライフが始まるんだ。以上、めでたし、めでたし、だね。
わたしたちが神様抜きで自分が死ぬことを考えるとき、そこには虚無感だけが漂う。自分が死んでいき、そしてすべての人から忘れ去られる冷徹な運命のもとにあることを直視せざるをえなくなる。でも、神様ありで、天国ありで考えるとしたら、そこには希望しかないんだ。そうなったら、もう忘れられるとかどうとか、うだうだ考えなくて済むんだよ。わたしはこのキリスト教のいわば反則技(?)に救われている人間で、もしもこれがなかったら今ごろ絶望して自ら命を絶っていてもうこの世にはいないかもしれない。それくらいこの教えには救われている。
で、もしもキリスト教の教えが単なる作り話で事実でなくて、最後の審判も復活も天国もなかったとしたら、その時はただただ残念に思うまでもなく、ただ無として無のままひたすら無でいることになるだろう。もうそうなったら、仕方がないと思っている。それに無は無でまた満更悪いものでもないかもしれないしね。だから、どちらにしろわたしにとっては問題がない。
でも、わたしのこと覚えてくれている人がいたとしたら、それはそれで嬉しいね。それは否定しないよ。

エッセイスト
1983年生まれ。
静岡県某市出身。
週6でヨガの道場へ通い、練習をしているヨギー。
統合失調症と吃音(きつおん)。
教会を去ったプロテスタントのクリスチャン。
放送大学中退。
ヨガと自分で作るスパイスカレーが好き。
茶髪で細めのちょっときつめの女の人がタイプ。
座右の銘は「Practice and all is coming.」「ま、何とかなる」。