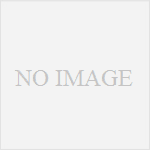先日、ある人と話をしたら、「あなたはみんなから浮いているよね」と指摘された。それを聞いた時、その通りだと思った。だって浮いていると自分でも思っているし、そのことに気付いていたから。
でも、人から面と向かって「浮いてるね」と言われてしまうのは何かこたえるし、グサっとまではいかないものの、それなりにダメージを受ける。自分で分かっている。分かっていながらも人からあからさまに言われると面白くない言葉ってあるんだなって思った。
この「浮いている」という言葉を言われるとどうしてあまりいい気がしないのかと言えば、やはりこの言葉自体に浮いていることを良くないことで、浮いていない、つまりは、沈んでいてみんなと同じようにしている方がいい、という価値判断が含まれているからだ。そう、ネガティブな意味合いがこの「浮いている」という一言には込められている。だから、「素敵だね」「かっこいいね」「きれいだね」「クールだね」などというポジティブな言われて嬉しい言葉とは違って、「浮いてるね」と言われて、「わたしはね、浮いているんだよ!」と満面の笑顔で喜ぶなんていうことはまずない。
日本人は調和や、その場の秩序を重んじるところがやはりあって、それを乱す人は「浮いている」ということになり、もっとまわりに合わせなさいということになるのだろうと思う。国や社会やコミュニティなどの集団を一つの大きな機械にたとえるなら、それに所属している一人ひとりは、一つの歯車。だから、その歯車は規格外であってはいけない。それが個性的でユニークすぎると(違う形の歯車だったりすると)、そこがうまく回らなくなってしまうから、まわりに迷惑がかかる。結果、全体の一つの機械が動かなくなって支障をきたすからそれでは困るのだという話。あるいは、その集団全体を機械ではなくて、音楽のオーケストラだと考えてみてもいい。みんなで一つの曲を演奏しようとしているのに、そこにそんなことお構いなしに好き放題に勝手な音を出す人がいたら、せっかくの曲がメチャクチャになって台無しになってしまう。この現実の国や社会などという集まりがこの一つの大きな機械やオーケストラで奏でる曲というたとえに完全に一致するかどうかは置いておくとしても、全体の和や協調性を重視する人たちは、浮いているように見える人たちのことをよくは思っていないようだ。
けれども、浮いてるということは悪いことなのだろうか。いけないことなのだろうか。たしかに浮いている人という大きなカテゴリーの中でも、他の人に危害を加えたりして迷惑をかける人は良くないと思う。ただ、そうした人たちはともかく、この世界は浮いている人たちによってリードされて刷新され続けてきたのではないかと。大抵、いや、パイオニア(開拓者)はみんな変人だ。歴史を大きく動かす人たちはみんな変わっている人たちで、普通の人たちがその変人たちの指し示す考えや方向などをいいなと思って、支持して従って、そして多くの人たちが動くことによって歴史は作られてきたのだと思う。坂本龍馬、織田信長、スティーブ・ジョブズ、ビル・ゲイツ、アインシュタイン、みんな変わった人たちだった。まわりから浮いているかどうかと言えば、明らかに浮いていた人たちだった。
言うまでもなく、普通のことを浮かないように普通の感じでやっているだけだったら何も面白くないとわたしは思う。浮かないようにするということは、みんなと同じように沈んでいなさいということで、これを徹底していくとその人はモブキャラとなって、ただの誰にも気付かれない空気とか背景になってしまう。いるのか、いないのか分からない。または、いたとしてもあまりにも普通すぎて目立たないものだから、「あれ? いたの?」となってしまう。いてもいなくても同じで、取り替え可能な存在でしかない。
もしも、この世界や日本全体をみんな同じようにしたいのなら、やることは簡単だ。SFめいた話になるけれど、人間は1種類だけいればいい。地球上にいる80億もの人たちすべてがみんな同じ顔で同じ体で同じ性別でいいことになる。
「違いは必要ない」をどこまでも追求していくと、みんな同じになる。1人の人間のクローンがとにかく大量にいる。そんな世界、楽しいのだろうか? 刺激的で面白いと言えるのだろうか? でも、たとえそういった世界が実現したとしても、その遺伝子が全く同じ人たちしかいない中で自分は他の人とは違うという個性を出そうとすると思う。髪型を人と違うようにしてみたり、人と違う服を着てみたりと試みるはずだ。と、個性を出そうとする人たちをもしも、その国家が統制して同じ髪型や服装などにさせたら息苦しくなり過ぎて暴動が起こる、なんていう話になっていくのではないか。
あるいはそこまで徹底しなくても、今のこの世界ですぐにできることとしたら、みんなお面をかぶればいい。同じお面をかぶればいいんだ。そして、同じ服装をさせればいい。それから、思想も統制するために決められたこと以外の話をしてはいけないように法律で定めて、一家に一台、カメラを設置して、会話も含めて監視する。それを人間が監視するのが難しければ(あまりにもカメラの台数が多いから)AIなどを用いれば十分できるかと。浮かないようにするを徹底すると、そう息が詰まる。
いや、わたしのことを浮いていると指摘した人は、何もそうした極端な世界にすべきだと言いたいのではなくて、この世界が学校だとしたらちゃんとみんなと同じ制服を着て、問題がない範囲で行動して、まわりに合わせて風紀を乱さないように、秩序や和を壊さないようにということだったのかもしれない。もちろんわたしはこの場合の校則(現実では法律)は破っていないから、そこまでいかないにしてもみんなと同じようにしましょう、ということなのかなと思う。
この「浮いてるね」という言葉にはすごい同調圧力を感じてしまうのだけれど、それは「大人になりなさい」ということでもあるのだろう。
大人。大人は自分の思ったことをすぐに口にしない。奇抜な言動や格好はしないし、反体制的なことをして反抗したりもしない。良識や常識を重んじて、まわりの空気をしっかりと読んで、場違いな言動も避ける。自分が自分がと自分ファーストではなくて、まず相手のことを考えて気遣って配慮する。その場や集団の調和、秩序を重んじる。日々、真面目に仕事をして働き、家庭を持ち、社会的な責任をしっかりと全うする。
そういう観点からすると、わたしが「浮いているね」と言われてしまうのはもっともなことだ。つまり、成熟していない。年齢的にはもう40代でいい歳をしたおじさんなのに、精神的に幼くて、言動が子どもっぽい。実際、わたしが20代後半か、いって30代前半くらいにしか見えないのは、肉体年齢が若いこともあるものの、やはり大人になれていないのだろう。青年期をとっくに終えているはずの年齢なのに、青臭いことをまだ言っているのはその期間を卒業できていない証拠で、若者臭さが抜け切れていない。
わたしのことを浮いていると指摘した人はさらにこんなこともわたしに言う。「他のみんなは、社会生活を送って気配りや気遣い、適切な対応などを何年もかけて学んできています。その間、あなたはそういったことをしてこなかった。だから、みんなから浮いています」。これは、イタタタなツッコミで、というか、もっともな指摘すぎてわたしは何も言えないし、返す言葉がない。
でも、その「みんな」というのは絶対的な存在で正しいのだろうかとわたしはどうしても反論したくなってしまう。みんなは、言い換えれば多くの人たちのことだ。そのみんなは社会生活を送ってきていて、他者を思いやる適切な心遣いや配慮などができて場違いなどぎつい言葉を発したりもしない。たしかにそれは日本的なあり方としては美徳そのものだろう。人間的にちゃんとしていて、落ち着いていて、立派なできた人だとみんなからほめられる。それが縁談やお見合いなら、なおのこと、長所として際だってポイントは高い。
けれども、それは一般的な話としてはということであって、それが必ずしもすべての場合に当てはまるわけではない。
最近、読んだ話でこんな面白い話があったので紹介させてほしい。何でも、その本によると、世間一般では空気が読めないとか場違いなことを言うなどと否定的にとらえられがちな発達障害の人の問題がある言動であっても、発達障害の人たちが集まって話をしている時には何も問題にはならないらしいのだ。むしろ、その場においては、発達障害ではない普通の人の言動のほうが場違いで空気が読めないということになるらしい。これはもっともな話で、話をしているグループの参加者たちが下ネタしか話さなくて、そういう話をテーマに決めている時には、そういう話題を避けることは場違いだ。そういう話を避けようとすれば「お高くとまってるなよ」と言われるだろう。つまり、世間一般、みんながNGだとしている言動であっても、その集団の中で良しとされていれば良しになる。それが倫理的、道徳的、法律的にどうかということとは関係なく、その集団の中で普通であれば普通ということになり、何も問題にはならない。だから、みんなが普通に足腰が悪くて、車椅子に乗っていて、1億総車椅子社会ならそれは障害でも何でもなくなる。その社会では、車椅子に乗っていないほうが普通ではなくて障害があることになるだろう。
そうか。要するに、「あなたは浮いてるね」と言うことは別の言い方をすると、「みんなは正しいのだからそのようになりなさい」ということではないか。でも、みんなはたしかに数が多いけれど、果たしてそのように振る舞うことが正しいかどうかと言えば絶対ではないはずだ。それは世間や社会一般という集団においては良しとされていて正しくて好ましいこととされている。でも、その集団が別の集団になれば、今度はまたその集団の中で良しとされることは自ずと変わってくる。わたしが空気を読めなくて、場違いなどぎついことを言ってしまうことや、大人になりきれていない子どもっぽい言動などもそれを問題としない人たちの間では問題にならない。いや、むしろ、「あなたはすごく面白いね」「最高だね」などとほめられて良い評価をしてもらえるかもしれない。もっと極端なことを言うなら、無人島とか山や森の中などの人が誰もいない場所では、みんなどころか自分以外には誰も人はいないのだから、自分がいいと思っていればいいというだけのことになる。または、もう少しその集団の人数が多くて関わる人の数が5人だけなら、その5人に受け入れられる言動をすればいいということになって、その際には、日本とか日本以外の世界の多くの人たちがいいと思うこと(思想、価値観、言動など)はあってもないようなものになって関係なくなってどうでも良くなる。
「みんなと同じようにしなさい」「みんなから浮かないようにしなさい」と求めてくる人には一言、「その『みんな』というのは誰のことですか?』と聞けばいいことになる。そして、「そのみんなは絶対的に正しいのですか? みんなは神様なのですか?」と聞けばいい。みんなというのは、所詮と言ってしまっていいのかは分からないけれど、個人がたくさん集まった集団でしかない。だから、ただの1人の人間がたくさん集まっただけの存在でしかない。
みんなは必ずしも正しいのか? そうとは言えないと思う。過去にそのみんなが独裁者に煽動されて、その言葉に熱狂さえして特定の人たちを大量虐殺したということが過去の歴史においてはある。王様などの支配者が自分が気に入らない人間を殺すことができないように、いろいろな仕組みができて今に至っている。王様がある個人を正当な理由もなく殺すことは良くないし、容認できないだろう(「こいつ、目つき悪いから殺す」などという理由で)。それと同じように、それが王様ではなくて、「みんな」という多くの人たちであっても正当な理由もなく人を殺してしまうのは良くないだろう。みんなが正しい、みんながいいって言っているからいいんだ。どんなことであってもみんながいいって言えばやっていい。数こそ正義であって力なのだから。昔、ビートたけしが「赤信号みんなで渡れば恐くない」という不謹慎なこと(おそらくギャグとして)を言ったけれど、みんなが言うことが、みんなが言っているからということで正しいなら「みんなで殺せば恐くない」となり、みんなという絶対的な王様が誕生してしまうことになる。で、ちょっと付け加えると、少し前のところで「正当な理由もなく」ということを言ったけれど、正当な理由があれば人を殺してもいいという正当な理由というのは果たして正当で正しいと言えるのか、とも言えるわけで、その正当かどうかという基準は絶対的なものではない。となれば、やはりそこで神様とかを持ち出してきて、絶対的に正しい神様はこう言っているから、だから正しいんだと権威を持ち出して言うしかなくなる。
わたし自身を見てみれば、言動がまわりから浮いているだけではなくて、やっていることも浮いている。ケータイを持たず(ガラケーを最近、解約して家の置き電話のみ)、ネットを使わない生活をしていてスクリーンを見ない生活を始めたところだし(入力専用端末のPomeraだけは例外的に使用。この文章はPomeraで書いている)、テレビ、ラジオ、ビデオなども断ち、お茶やコーヒーなどのカフェイン飲料を一切飲まず、ヨガを習っていて、公衆電話をテレホンカードを使ってかけている。多くの人にとっては、このネット社会のご時世でネットを使わない生活なんて正気とは思えないだろうし、今時、公衆電話でテレホンカードなんて変人そのものだろう(高齢のおじいさん、おばあさんであってもガラケーなどを持っている)。でも、わたしはこの生活が気に入っていてすごく心地いい。コンタクトレンズなど(ネットではなく実店舗だと3倍近い値段になってしまうため)本当にどうしてもという時には母にスマホを貸してもらうという反則技を例外的に繰り出すものの(あとはブログに文章をアップして更新するために1ヶ月に1回くらいノートパソコンを使うくらい。使ったらまた物置へ移動)、それ以外はネットを使わない生活を始めてみて、すごく頭も体も軽快になってメンタルも良くなった。どうして20年間もやめないでやってきたのだろうというくらいの心地良さがあった。いろいろやってきて、いろいろやめてきた中でも、このネットフリーにしたことは想像以上に効いた。
みんなはたぶんこう思っているし、言うことだろう。「ネット社会なんだからさぁ、スマホくらいは社会人のたしなみとして持ちなよ」「今時、公衆電話なんておかしいよ。ガラケーくらい持ったらどうなの?」と。
言うまでもなくわたしは変だし、おかしい。やっていることが普通ではない。でも、いいんじゃないのって思う。だって、自分がいいと思っていて、それが心地良くて楽しいのだから。それを批判したり否定して難癖つけてくる人は責任は取らないだろうし、取れるわけがない。わたしはわたしの人生をいいと思ったように生きて死んでいくだけだ。だから、ネットをやっている圧倒的多数の人たちを否定してけなしたりはしない。ただ、「ネットは体に悪いよ。メンタルにも良くないし、頭にも良くないよ」とは個人的な意見として言い続けるだろうとは思う。
そんなどう見ても変人で、世間から浮いているようにしか見えないわたしのことをいつも見ている母は冷静にこう分析したのだけれど当たっているのだろうか。「大地は浮いているんじゃなくて頭がいいから結果的にやっていることがみんなと違う感じになるんじゃないの」と。おぉ、素晴らしき理解者であるまさにグレートマザーな母。
多くの人たち、みんなである世間はわたしのことを空気が読めなくて、言動が変わっている変なやつだ。もっと大人になれよ。ちゃんとしろよ。世間に合わせろよ、と大合唱のごとく冷たい視線を浴びせかけてくることだろう。わたしが何か言うたびにしら~っとあきれた顔で、蚊帳の外に閉め出して、自分たちの前に「入ってくるな」とシャッターを下ろすことだろう。わたしはうっとうしい蚊帳の外にいる蚊、または自分たちのちゃんとした世界をその非常識な言動(日本人にとっては)でかき回す外国人のような存在(下手したら外国人どころか宇宙人扱い?)。
そうなったらわたしを面白がってくれる数少ない人を探せばいい。ネット断ち同好会とか公衆電話同好会とか作れば誰か来てくれるでしょ(作ろうとは思わないけれど、たとえばの話)。少ないけど何人かは。
みんなから浮いて浮いて、どこまでも浮いていってその先にどこへ行くのか? あ、でも、このわたし程度の浮き方では大したことないらしいですよ。変な人は世間にはいっぱいいますから。わたしは、ちょろっと普通の人にかわいい毛が生えた程度でしかないので。で、全日本変人選手権でもやったら凄まじい異様な雰囲気になるだろうなと思うけれど、これは絶対、開催しない方がいい。もはや、テレビなどでは放映できないはず(変な人どころではなくて変態の集団になること確実)。
10年後、20年後、わたしは何をしていてどこにいるのだろう? もしかして、インドの森の中に住んでいたりして? それも浮いてますね。変だと思います。変わっています。でも、だからこそ個性的で面白くて楽しいと思いますけど? ダメなんですか? みんながそう言うから? だから、そのみんなって誰なんですか? 数は正義で絶対で真理なんですか? 「10万いいね」だろうが「100万いいね」だろうが、それ以上だろうが、わたしにとって面白くなくてつまらないものはわたしにとっては退屈そのもの。
小学校1年生の時に、小学校と中学校の9年間で1回だけ出た幻の給食のメニューのオレンジご飯。あれ、最高だった。あれが学校の給食で食べた中で一番美味しかった。ほとんど全員がまずいと言って残して大量に残ったそのご飯。だから、数じゃない。みんながどうかではない。今、そう思う。
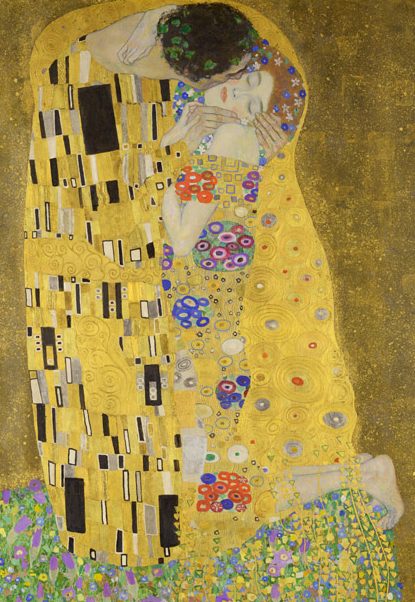
変な人。
普通ではないと思う。
わたしが思っていることを言うとみんなひく。
そして、目の前にシャッターを下ろされて、
まさに閉店ガラガラ~。
わたしは気が付くと蚊帳の外。
なぜなら、今、大人気の
カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。
最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。
そう、なんか浮いてるの。
この世界、日本という社会から。
わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。
「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。
お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、
苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。
その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。
気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。
わたしはしゃべんないほうがいいと思う。
しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。
わたしが自分のことを語れば語るほど、
女の人はがっかりします。失望さえします。
でも、いいじゃないの。
普通じゃないのがわたしなんだから。
わたしは風になりたい。
風になってただ吹いていたい。
【属性】
男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。