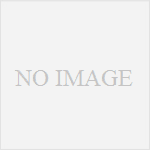あともう少し読めば読了、というところで興味・関心が他のことへ移っていき、しばらくこの本を積ん読していた。2ヶ月くらいは放置していただろうか。だから、多くを忘れてしまっているから、内容を網羅的に語ることなどできないし、レビューとか感想としては不十分なものなのかもしれない。しかし、それでも書く。書きたいからだ。
クリスチャンのわたしは、世界というものは神様がつくられて、そしてわたしも含めた森羅万象が神様の作品なのだから、その一つひとつには揺るぎない確固たる価値があって、だから、意味があるんだと考えてしまう。たしかに、それはわたしの信仰として尊重されるべき事柄ではあると思うのだけれど、もし神様がおられなくてただ無神論的にこの世界があるのだとしたらどうだろう。その視点からすれば、いや、たとえ神様が万物をつくられたとか、そうでないとかそういうことを抜きにしても、在るということは驚きのあまり言葉を失ってしまうようなことだ。
わたしは統合失調症なのだけれど、調子が悪くなって感覚が過敏になってくると、決まって在るということがとても気味が悪くなってしまう。目の前に広がる光景が薄気味悪くなってしまうのだ。それは病気だからだと一言で片付けようと思えばそれで終わってしまうことなのかもしれない。でも、もしかしたらだけれど、わたしの鋭敏になりすぎた感覚が真理の一つの姿を垣間見ているのではないかという気がしてくる。
在るということを薄気味悪く思うのも、それに驚愕してただただ存在神秘に畏敬の念を持つのも、ネガティブかポジティブなのかベクトルは逆だけれど、存在というものに何かを感じているという点では同じだと思う。
そもそも在るってどういうことなんだろう、って考えていくと、在るんだから在るってことだろとしか言えない。科学的に考えれば、在るってことはそこにエネルギーがあることを意味する。物質をどこまでも細かく見ていくと最終的には素粒子になる。その素粒子が運動をしている。ってことはこの世界はすべて目に見えないものからできているんだ。目に見えないくらい小さなものの運動によって成り立っているんだ。でも、その素粒子というかエネルギーがどうして今ここにあるんだろうと問うていくと、わたしの予想では科学には答えが出せない。むしろ、それは宗教とかの領域で、なぜには宗教が答えるしかない。
わたしが調子が悪くなると陥る不調は、目の前のものが在ることが不気味で不気味でこわくて仕方がなくなるというもの。そして、この目の前のものが過去・現在・未来へと存在していて、今あって、そしてこれからも存在していくことへの恐怖感。つまり、得体が知れない現象が目の前で起こりつつあることへのネガティブな驚愕なんだと思う。
在るということはいたってシンプル。在る。在る。たしかにある。あるんだから在る。その根拠は? わたしの五感がそれをあるんだと認識している。だから、在る。そうとしか言えない。
じゃあ、わたしの五感がないものを、つまりこの世界は存在していないのに、それをあるのだと錯覚しているのだとしたら? あるいはわたしの五感が狂っているのだとしたら? 五感を信頼できないとしたら? たちまち、自分の信じている、そして今まで信じてきた世界はおぼろなものになり、もしかしたら自分は幻想の中にいるだけなんじゃないかって思えてくることだろう。幻想、あるいはこの現実だと信じている世界は夢なのかもしれない。それをひっくり返すことってできないだろうと思う。
でも、こういう哲学病にかかってしまうと、現実生活を送れなくなってくるから、青年はキリのいいところで疑うことをやめて、「この世界はたしかに存在するんだ」と思考停止して、そういうもんだと割り切って生きていこうとする。
こういうことを言うと人格を疑われるかもしれないけれど、わたしはもしかしたらこの世界は全部幻かもなって思ってるよ。けれど、とりあえずこの世界は今んところ続いているし、このまま続いていきそうだから、この枠組みの中で普通に生きている。それが実態だったりする。
わたしは「在る」の前で佇んでいる。そして、時折、驚愕に打たれながら、時折、不思議な感覚に包まれる。
とここまで本のタイトル「瞬間を生きる哲学」の趣旨に反したことを書いてきてしまった。これでは「瞬間を疑う哲学」だ。
でも、本当に無我の境地に至った時には瞬間を生きることもなくなると思うのだ。ただ、静かな何もない無の中を静寂が包んでいる。というか、そこには静寂すらなくて、ただただ無があるのみ。気持ちいいとか、瞬間の歓喜とか、生の充溢とか、その反対の嫌悪、苦悩、倦怠。そんなものはそこにはない。ただあるのは無。そして、時間すら流れていない。原初の状態へと帰るというのはそういうことではないかと思う。それこそが安らぎをも越えた本当の安らぎ。
わたしは天国という場所をとにかく気持ちがいい場所だと今までは想像していたのだけれど、天国はもしかしたら永遠の平安であって無なのかもしれないなとも思うようになってきた。天国がどのような場所かは神様だけがご存知のこと。天国には神様もイエスさまもいないのかもしれない、なんてクリスチャンのわたしが言ってしまっていいのかは分からない。けれど、それはその時になってみないと分からないことだ。わたしはまだ死んではいないし、生きている人間で天国に行ったことのある人間はいないのだから(聖書では預言者が天国の姿をリアルに見たという話があったとは思うけれど)。
正確には、わたしたちはこの自分を含めた世界があるのかどうかさえも証明することができない。ただ五感に頼って、あることにしているだけで。すべてが空であって、何もそもそも存在していないのかもしれない。でも、そうであってもわたしたちの(仮にあるということにしている、そうだと信じている)世界はこれからもしばらくは死ぬまで続いていく。
不思議だ。不思議だ。本当に不思議だと思う。在るということが。そして、この世界をわたしが在ると思えること自体が。存在を存在としてわたしが認識しているということが。すべてが不思議で、不可思議でこの世界って一体何なんだろうとさえ思う。ないのかもしれない世界であるのだと信じながら生きていくわたしたち。あるのかなぁ? それともないのかなぁ? それすらも神秘に包まれている。在るというこの当たり前のことが持っている神秘について考えさせられた今回の読書であった。
在るって本当、不思議。

エッセイスト
1983年生まれ。
静岡県某市出身。
週6でヨガの道場へ通い、練習をしているヨギー。
統合失調症と吃音(きつおん)。
教会を去ったプロテスタントのクリスチャン。
放送大学中退。
ヨガと自分で作るスパイスカレーが好き。
茶髪で細めのちょっときつめの女の人がタイプ。
座右の銘は「Practice and all is coming.」「ま、何とかなる」。