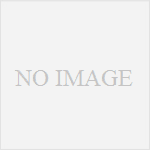今日は、教会の聖書研究会の日で、わたしも出席してきたのだった。
今日の牧師のお話の中で一番印象に残ったのが地獄の話だ。
わたしは割合聖書を額面通り受け止める方だから、聖書にある「地獄」という単語に翻弄されつつここまで歩んできた。地獄を恐れて、どのようにしたら自分が地獄行きにならずに済むのか。どうしたら天国へと行くことができるのか、と思案してきたのだ。わたしがキリスト教の洗礼を受けたのも、天国へ行きたいという思いが強かったからで、わたしにとって天国と地獄という考えは、まさに事実の出来事としてリアルに迫ってきていた。
そんなわたしだったから、牧師が地獄というのは観念でしかない、ということを言った時には言うまでもなく、面食らわされた。「えっ? 地獄ってないの?」と今更ながら驚かされたのだ。だって聖書には地獄が云々ってあるじゃないですか。それすらも牧師は教会が過去の歴史において作り出してきたものでしかないと言う。
この科学が発達した現代において、地獄がどうこうと発言しても大して人々には受け入れてもらえないことだろう。世界は世俗化してきていて、そういうのは迷信だと言って退けることだろう。
でも、わたしは地獄がもしかしたらあるんじゃないか。キリスト教の歴史の中で地獄の思想が醸成されていた時代があったように、実際に事実関係として地獄があるんじゃないか。そんなことを今日、牧師の説明を聞きながら思ったのだ。
わたしは以前、すべての人が救われて天国に入るようになってほしい、といったことを願っていた。今でもその思いは変わらず、と言いたいところだが、そう単純明快にはいかなくて複雑な思いでいる。なぜなら、世界は幸せに満ち溢れていながらも、一方では殺戮と破壊と狂気に包まれているからだ。人がたくさんいれば必ず犯罪が起きる。それをゼロに近づけることはできるけれど、どんなに頑張っても一定数発生してしまう。人は殺し合う。憎しみ合って、限りない怨恨の連鎖が続いていく。
そんな血みどろの状況下において、「どんなに悪いことをした人だって救われて天国へ行けるんですよ」とはっきり言ってしまっていいものなのか。わたしがこうしたことを数年前にある牧師に質問してみたら、「悔い改めなければ救われません」と答えてくれたと思った。悪いことをしたのにそれを何も気に留めず悔い改めない。反省しない。それではダメだと言うのだ。その牧師はおそらく地獄の存在を確信していたんじゃないかって思う。
地獄。果たしてあるのかなぁ。それともないのかなぁ。どんなに考えても、議論をしてもらちが明かないことはたしかで、はっきりとしたことは最後の審判が行われる時まで分からないのだ。死後の世界、というものは聖書にはこう書いてあるからこうなんじゃないか、仏典にはこう書いてあるから、などと推測することしかできなくて、実際、どうなのかということはヴェールに包まれているのだ。いろいろ推測することはできる。こうじゃないかと考えることもできる。でも、本当はどうなのか、という素朴な疑問は生きている間には解消されない。いわば神秘の領域である。死んでみなければ分からないのである。死後の世界がどうなっているのか、ということは(あるいは死んでも分からないかもしれない)。
ということは、宗教者が人類の歴史において、こうすれば救われますとか、ああすればいいですよ、などと言ってきた膨大な言説が下手をしたら全部サギだったということも十分ありえるかもしれないのだ。宗教者が民衆からお金をもらって魂の平安を保証してきたものの、それらの営みすべてが真っ赤な嘘で嘘つきも大概にせえよ、てな事態になるかもしれないのだ。死んでみたら天国も地獄もなくて、ただ死んで何も分からなくなっただけ。宗教の言説は全部作り話で嘘だったよ。そんな身の毛もよだつ話が現実のものとなるかもしれないのだ。
しかし、わたしはもしキリスト教が嘘だったとしても、それはそれで意義があったと思うのである。晴佐久神父が神学生時代、共同幻想という思想にぶつかって、全部嘘じゃないかっていう思いにつぶされそうになったらしいのだが、彼はそれだったらそれでもいいじゃないかと開き直ったのだと語っていた。素晴らしき幻想ではないかと。つまり、人を幸せにする嘘だったのだ、と。少なくとも、キリスト教は真偽はともかくとして、人々に生きる希望と活力を与えている。幸せな神の家族をつくりあげて、多くの人々を孤独から解放している。それのどこが悪いんだ。たとえ、キリスト教が嘘だったとしても、これはこれでいいじゃないか。
わたしは信じている。何を? イエスさまを。最後の審判と天国と地獄の存在を。でも、もしかしたらそれらが単なる作り話であるかもしれない。だったらいいさ。その時はその時だ。信じて裏切られたとしたら、もうそれは仕方がないことだ。つまり、なるようにしかならない。事実、そうであるようにしか物事は進んでいかないからだ。天国と地獄があるなら、そのように物事は進んで行くし、ないならないなりに進んでいく。ただ、それだけのことだ。
もしかしたらだけど、唐突な話、ある銀河系からやってきたメロンによく似たメロン星人としておこうか。そのメロン星人が実はこの宇宙を取り仕切っていて、この人物が神様で、死んだ人間をメロンに変えて、それはそれは安らかなメロン畑を地球上に作り上げる。そして、人々は朽ちないメロンとなって生き続ける。このふざけまくっているようにしか思えない荒唐無稽な話であっても、それが100%ありえない、と誰が断定することができようか。もちろんこんなふざけた話をわたしは信じようとは思わないけれど、それでもその可能性はゼロではない。これが真実であるということもあるかもしれない。
つまり、実際に自分が死んでみなければ本当のところは分からないのだ。信じているものがあるにしろ、ないにしろ、ともかく死んでみなければ詳細は明らかにならない。だから、メロン星人は荒唐無稽すぎてお話にならないかもしれないけれど、それでも「分からない」と断定を避ける謙虚さが必要だとわたしは思うのである。本当の知者、本当の賢者は分からないことを分からないと惜しげもなく言うのではないか、という気がする。まるでソクラテスのように。逆に何でも分かっているのは神様だけで、有限な存在である人間には知り得ないことがたくさんあるのだ。全く何も知らない無知とまではいかなくても、知らないこともある。「分からない」の深みをここで感じるわたしなのだ。一見、答えることから逃げているだけのように見えなくもないこの言葉はとても深い。
地獄。そして、分からない。わたしが信じているものが事実であることを願いながらも、ある場所まで行くと、沈黙せざるを得ない。それが人間としての限界であり、神様に造られた被造物として越えてはならない線なのだと思う。そこを越えようとする時、人間は傲慢になり、謙虚さを忘れてしまう。そして、全能感に包まれて自分を神にしたくなってくる。わたしは神様ではないし、神様にはなれない。そのことだけわきまえていれば大丈夫。そんな危ない予感を横目に眺めながらわたしは佇む。

変な人。
普通ではないと思う。
わたしが思っていることを言うとみんなひく。
そして、目の前にシャッターを下ろされて、
まさに閉店ガラガラ~。
わたしは気が付くと蚊帳の外。
なぜなら、今、大人気の
カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。
最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。
そう、なんか浮いてるの。
この世界、日本という社会から。
わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。
「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。
お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、
苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。
その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。
気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。
わたしはしゃべんないほうがいいと思う。
しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。
わたしが自分のことを語れば語るほど、
女の人はがっかりします。失望さえします。
でも、いいじゃないの。
普通じゃないのがわたしなんだから。
わたしは風になりたい。
風になってただ吹いていたい。
【属性】
男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。