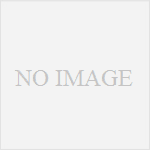40年あまりの人生を送ってきたわたしは今までいろいろな先生に出会ってきた。先生と言っても職種はいろいろで、学校の先生もいれば、お医者さんの先生もいれば、塾の先生もいれば、牧師もいれば、習い事の先生もいる。その中で、その中で、わたしに本当に光を与えてくれた人って誰だろうと思い出してみると、二人ばかり思い出す。一人は高校の時の先生。そして、もう一人は教会の牧師。
教会の牧師はわたしが死の問題で悩んでいて本当に暗い思いでいる時に、教え諭して光を与えてくれた。その教会にはもう行かなくなってしまったけれど(最近行かなくなった教会の前に行っていた別の教会)、それでもその時の牧師の一言が忘れられない。今、どうしているのだろう? いろいろあって、ほとんど何も言わずに去ってしまったわたしだったけれど、今も元気で、キリストの福音を宣べ伝えているのだろうか。
当時のわたしは、いつ、どこで、どのように死に、死んだらどうなるのか、といった問題と真正面からぶつかって、そして力尽きて折れて絶望していた。人はいつ、どこで、どのように死んで、死んだらどうなるか分からない。だとしたら希望なんて持てないんじゃないか。そんな風に思っていた。それに何か明日にでも交通事故なんかに遭って死ぬんじゃないか。そんな良からぬ不吉なことばかり、ぐるぐる、ぐるぐると考えてばかりいた。そんな調子でやっていれば、毎日なんて、死ぬまでの暇つぶしにしかすぎないという認識しか持てなかったし、だから、毎日刹那的に無為に過ぎていく。何をやっても結局死んでしまう。だから、何をやっても意味なんてないし、すべて無駄で無意味なあがきでしかない。これってものすごく青臭い考えだと今では思えるのだけれど、当時は本当に真剣に思い悩んでいた。死んだら死んだで仕方ないじゃん。みんな、どうせいつかは死ぬんだよ。だから、その死ぬまでの間を精一杯生きるんだ、みたいな生の輝きを賛美するような、そんな思想はこれっぽっちも持ってはいなかった。ただ、死ぬ。どうせ死ぬ。だから無意味。そんな調子の20代半ばから後半だった。
そんな青臭い悩みというか思いに対して牧師は「神様はあなたがいつ死ぬのかその死ぬ日すらご存知です。どのように死ぬのかということももちろん知っておられます。だから、思い悩むのではなくて神様に委ねてみませんか」といったことを言ってくれた。その時のわたしはまさにその言葉に本当に救われるような思いで、一気に肩の力が抜けて楽になった次第だった。
話が少しばかり長くなった。わたしが書きたいのはこの牧師のことだけではなくて、もう一人の高校の時の先生のことでもあるのだ。
高校時代、わたしは本当に孤立無援だった。中学校までは優等生として優秀な成績で通っていたものの、高校に入ってついていけなくなり、赤点を大量に取るようなそんな生徒となっていた。学校に行っても何も面白くなんかない。だって授業がさっぱり分からなかったから。何を言っているのか、日本語なのに理解できないし、理解する気持ちさえもなかった。だから、何にも理解できないのに、ただひたすら机に座って授業を聞いているふりをしている。そんな学校生活だった。授業が分からないというのは苦しい。なぜなら、学校という場所は大半が農業高校とか、そういった特殊な学校でもない限り、英国数理社のお勉強ばかりなのだから。わたしの人生において、あそこまで無意味で無駄な時間というのはなかったような気がする。が、中学校で結構有名人となってしまっていたから、高校を中退するとか、不登校の人向けのフリースクールに行くとかいう選択肢はなかった。人の目、世間体をものすごく気にしていた。今の高校を卒業すること。その一択しかなかったのだ。それに当時はまだ不登校というのが一般的ではなかったし、大学検定というものもまだまだ浸透してはいなかった。ある意味、そういうことをしているのは変わり者、それも本当に弱いダメな人という偏見すらあったような時代で(もちろんそんなことはないのだけれど)、そんなわけでわたしの我慢に我慢を重ねた無為で無気力な生活は続いていたのだった。後にわたしはその無気力感を心理学で言うところのたしか学習性無力感だと知るのだけれど、この無力感は自己肯定感をものすごく低くしてしまう。よく心理学の実験でラットを使うでしょう? そのラットを飼育箱の中に入れて電流を流す。その時にその電流を自分の行動によって止めることができるとそのラットは無気力にはならずに済む。が、どんなにあがいてジタバタしても「やっぱりダメなんだ。何をしてもダメなんだ。この苦痛からは何をやっても逃れることはできないんだ」とばかりに、自分の行動によってどうにもできない状況が続くと、つまり、あきらめてしまうとそのラットは何もしなくなる。ただ、苦痛に打ちひしがれているだけで何にもしない。そう、それが学習性無力感。わたしもそのラットと同じように、ひたすら分からない授業を一方的に聞かされて、その不快感を何をやっても解消できないような気持ちにさせられてしまっていたから、もうとにかく無気力になっていた。だから、何かアクションを起こそうとさえしない。「ダメなんだ。この苦痛から逃れる方法はないんだ。こうしているしかないんだ」とあきらめていた。今思うといくらでもその苦痛を回避できる方法はあるのに、とさえ思ってしまうのだけれど、当時のわたしはそんな檻の中に入って、別に扉は開いていたのに出られないと思い込んでその中にいる。そんな無気力なラットのような存在だったのだ。
そんな檻の中で囚われているようなわたしにある先生はこんな言葉をかけてくれた。「ぼくは君の味方で応援してるから」。その言葉を聞いた時、あまりにもその言葉の衝撃が大きすぎてしばらくは何を言われたのかぼんやりとしていた。でも、家に帰ってからその言葉を思い出すと、涙が出るくらい嬉しくなってきた。はっきり言って、みんな敵とはいかないまでも味方ではないと思っていた。誰も味方にはなってくれていない。わたしはほぼ一人。学校では毎日お昼にみんなが楽しそうにお弁当を食べている中、3年間独りで食べ続けていたし、ある時なんてその様子を見かけたまた別のある先生が「寂しい食事だ」と言ってそこにいた他の生徒の笑いを誘って、実際にみんなに笑われている始末。人って自分だけ良ければそれでいいんじゃないの? そう思っているんじゃないの? だってわたしが独りでお昼を食べているのに誰も声をかけてくれないし、関わろうとはしてくれないんだよ? それがれっきとした証拠でしょ。そんなことさえ思っていた。
そこへ「ぼくは君の味方で応援してるから」という奇跡のようにさえ思える言葉。どれだけその言葉の暖かさのようなものに救われたことか、光が差し込んできたことか、言葉では言い表せない。
それからその先生と何か特別懇意になったとか、そういうわけではない(ちょっと期待したでしょう? 今でも親交がその先生とあって恩師として慕っているとか)。卒業してから何も連絡もしていなければ、葉書の一枚さえも出していない。でも、その時のあたたかくなった、あたためてもらったその時の今にもわぁぁってなってしまいそうな嬉しさは今でも覚えていて忘れてはいない。
わたしに教育について語る資格はないとは思うけれど、教育というのは「あなたは素晴らしい存在ですよ。そして、わたしはあなたの味方で応援していますよ」というメッセージを伝えるものだと思うのだ。英語の知識とか、数学の知識とかそういったことを教えるのが先生の役割だと言ってしまえばそれまでかもしれないけれど、それだけではなくてもっと重要で大切なことは生徒に教師が肯定的なメッセージを送れるかどうかというところにあるはず、とわたしには思えてならない。勉強を教えることができたとしても「あなたはダメな存在で価値がなくて、わたしはそんなあなたの味方ではないので勘違いしないように」なんていうメッセージを生徒に教師が送ってしまったら、勉強はできるものの嫌味で高慢で生意気な人間が出来上がるだけだと思う。それにそこまでドライな関係や態度で人が育っていくのだろうか。
嬉しかった。あの言葉、その時はすごく嬉しかったけれど、ついさっきまで記憶の箱の中に入れっぱなしになっていて思い出せずにいた。でも、それを思い出したら何か、わたしの暗黒の高校生時代にもいい先生がいて、必ずしも100%真っ暗ではなかったんだなっていうことに気付けた(あと高校生の時の明るい思い出と言えば、校内の球技大会の卓球で三連覇したことと文化祭で劇をやったことくらいだろうか)。
わたしもあの先生のように誰かに「わたしはあなたの味方で応援しているよ」というメッセージを送れているのだろうか。規模は、範囲は本当にたかが知れている狭いものなのかもしれない。でも、影響力の大きさではなくて、たとえそれが一人の人にしか及ばなかったとしても暖かい気持ちにすることができればいい。できていればいい。何も大規模であることなんかにこだわらなくても。そう、たとえるなら三度三度の食事を家族のために作るインドのお母さんのような、そんな存在になれればそれでいい。
先生からもらった暖かい言葉はわたしへとつながっていて、今も生き続けている。そして、さらにまた別の誰かへとつなげていけたらいいなというのがわたしの願いだ。味方で応援してるから、か。あったかい言葉だな、本当。
日本ブログ村のランキングに参加しています。
記事をいいなと思っていただけましたら、
下のバナーをポチっとクリックしてください。
クリックしていただけますと励みになります。
よろしくお願いします。
にほんブログ村

変な人。
普通ではないと思う。
わたしが思っていることを言うとみんなひく。
そして、目の前にシャッターを下ろされて、
まさに閉店ガラガラ~。
わたしは気が付くと蚊帳の外。
なぜなら、今、大人気の
カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。
最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。
そう、なんか浮いてるの。
この世界、日本という社会から。
わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。
「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。
お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、
苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。
その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。
気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。
わたしはしゃべんないほうがいいと思う。
しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。
わたしが自分のことを語れば語るほど、
女の人はがっかりします。失望さえします。
でも、いいじゃないの。
普通じゃないのがわたしなんだから。
わたしは風になりたい。
風になってただ吹いていたい。
【属性】
男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。