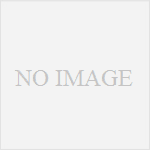わたしもかれこれもう40代で、何だかんだで40年近く生きてきた。そして、自分なりに本を読んだり、何かを体験してみたり、考えてみたりしてきたのだけれど、分からないことがたくさんある。
この分からないことをはっきりさせよう、白黒つけようとするところがわたしの悪い癖で、何もかも白日の下に晒したいと思ってしまう。でも、分からないんだ。何が? そう、一体、自分を含むこの世界、現実が何なのか、という最も基本的で当たり前でさえあることが。
ヨガの道場にかれこれ1年半あまり通って練習をしていたら、日が経てば経つほど現実感覚が希薄になってきて、何だかこの現実だと思っているこの世界がまるで夢とか幻のように思えてきて仕方なくなってきた。一体この世界は、現実は何なのだろうというのが正直な感想というか、思うところでまったくもってして分からない。不気味とか不可解で、だから死ぬしかないとかそういう感じでもないのだけれど、不思議で違和感があって、どうもしっくり来ない。
そんなこんなで日々を送り、毎日を過ごしていたらある本に「この世界では分かっていることよりも分からないことのほうが多い」という至極真っ当なことが書かれていて、それを読んだわたしは「たしかにそうかもしれない」と少し目が覚めるような思いがした。
人間がいろいろと経験値を増やしてきたからこそ、今の学問や知恵や知識といったものが集積されている。でも、それをもってしてもやっぱり分からないことは分からないのだろうと思う。わたしが今相変わらずつまずいている「この現実の世界は幻なのか?」というシンプルすぎる問いに対しても決定的な回答はないようだ。なぜなら、学問にしてもその中の知識にしても基本というか、ベースにあるのは知覚、要するに五感だからだ。この自分が見たり、聞いたり、嗅いだり、触ったり、味わったりといった感覚が本当の真実で欺かれていないかどうか、というところまで疑っていくとすべてが怪しくなってくる。わたしがあると思ってかたく信じているこの現実、世界は本当にあるのか? あるとしたら、五感に頼らないでそれを説明することができるのか? そう考えると何か超越的な第六感とか何とか怪しげな感覚やら能力を持ち出さない限り、たぶん無理だということに気付かされる。もしかしたら、この世界はそもそもないのかもしれない。存在していないのかもしれない。本当は何もなくて虚無そのものなのだけれど、なぜか(理由は分からない)あるように感じてしまっていて欺かれている。それが真実なのかもしれない。
だとしたら、つまりこの世界が幻なのだとしたらその幻の中で営まれるすべての行為やそれによって生み出される物や出来事なども幻なのだから意味がないということになる。いや、意味があるとしたら幻の中でだけ、この中にいる時にだけ意味があるというだけのことだろう。夜に見る夢の中で億万長者になったり、オリンピックで金メダルを取ったり、好きで好きで仕方がなかった意中のあの人と楽しい時間を過ごせたり、本当に幸せな時を過ごせたとしても、それから覚めてしまえばどこかむなしく寂しい。それと同じようにこの現実だと信じてやまない世界が幻だとしたら、一体、わたしの毎日の生活に何の意味があるのか? これは難問だと思う。
いや、そんなことはなくて、この現実は実際に自分がとらえて感じているようにちゃんとある。存在して実在している。本当にそうなのか確かめる方法はないにしても、仮にそうだとしてみる。けれども、人は必ず死ぬらしい。致死率100%で誰ひとり例外なく死ぬものらしい(「らしい」と断定できないのはわたしはまだ死んだことがなくて、死んでいった人のことしか見ていないから)。となれば、この現実が夢や幻ではなく実在していたとしても、夢や幻のようなものと言えるのではないかと。儚くまるで泡のように膨らんだかと思うとすぐに弾けてしまうような。
こういう感じでこの現実、世界があるのか、それともないのかと真正面からぶつかっていくと限界にぶつかって座礁する。知覚である五感で得ている感覚が本当に信用できるのかどうかとどんなに考えても、ただそのように受け取って感じている自分がいるだけでそれ以上のことは言えないし、分かりようがない。
最近ある人にわたしが現実感覚がなくなってきたという話をしたらその人は意外なことを言った。「この世界は神秘的ですよね」と一言。神秘的。わたしはその言葉に対して「良く言うとそういうことですよね」と少し皮肉混じりに聞こえる感じで返した(生意気だよね、わたしって)。
今、ふとこの「神秘的」という言葉からルター(世界史に出てくるキリスト教の宗教改革をやった人でプロテスタントの元祖)のことを思い出した。ルターは悪の問題について神学的な議論をした時に「神秘の領域」という言葉を持ち出して明確な議論を避けた。全能で愛なる神がおられるのにどうしてこの世界には悪があるのか、という最もシンプルでありながら最も難しい問題を前にしてツッコまれた時に「それは神秘だから分からない」という感じのことを言ったわけだ。これを批判者は「神秘の領域に逃げ込んでいるだけで答えていない」と厳しく攻撃した。
でも、考えてみれば、わたしはこの世界、そして最もよく知っていると思っている自分自身について一体どれだけのことを知っているのだろうか? 少しばかりの経験や知識をもとにして、まるですべてを知っているかのように振り回しているだけで、じっさいはほとんど何も知らないのではないか。20年前の自分と今の自分では今の方が経験や知識が増えたから少しは賢くなっているのかもしれないけれど、わたしが分かることはごくごくわずか。それは人類の知においてもたぶんそうで、分かっていることなんてまだまだごくわずかだと思う。分からないことの方が圧倒的に多いはず。人間にはこの最も初歩的でごくごく当たり前のことでさえある「現実があるのか」ということさえ分からない。あるようには見えるし、そう感じてはいる。でも、それが本当にあるのかどうかということはブラックボックスのような感じで究極的には謎なのだ。
「神秘的」という言葉は、この世界について何でも白黒つけようとしたり、まるで自分が何でも知って分かることができるかのように傲り高ぶっているわたしのような人間に謙虚であることの必要性をサラリと教えてくれている。
神秘か。たしかにすべてがもしかしたら神秘なのかもしれない。神秘的なのかもしれない。自分がいまここにこうしていること(あるいはこうしてあるように感じることができていること)を含めて、地球があること、生き物がいること、食べることによって命が養われていること、生きていること、死んでいくこと、等々。神秘を前にして「何で分からないんだ」と苛立つのではなくて、この神秘を前にして神などの大いなる存在に謙虚に頭を下げて、むしろ「このわたしに教えてください」とか「分からせてください」と求めていくあり方。そんなあり方もできるのではないか。
神秘。神秘的。とてもとても深い。その神秘は分からないこそ神秘であって、それも悪くないかもしれない。それだから美しいのだろう。なんてね。

変な人。
普通ではないと思う。
わたしが思っていることを言うとみんなひく。
そして、目の前にシャッターを下ろされて、
まさに閉店ガラガラ~。
わたしは気が付くと蚊帳の外。
なぜなら、今、大人気の
カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。
最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。
そう、なんか浮いてるの。
この世界、日本という社会から。
わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。
「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。
お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、
苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。
その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。
気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。
わたしはしゃべんないほうがいいと思う。
しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。
わたしが自分のことを語れば語るほど、
女の人はがっかりします。失望さえします。
でも、いいじゃないの。
普通じゃないのがわたしなんだから。
わたしは風になりたい。
風になってただ吹いていたい。
【属性】
男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。