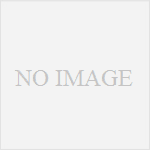訳あって洋服屋へと行ったわたし。そこはカジュアルな洋服のお店で、わたしには到底関係がない場所だった。が、入った。たまにはジャージではなくて、カジュアルもいいかなと思って。
入ってみたものの、全然心がときめかない。それに障害年金しか収入がない貧乏なわたしにとっては、そこでお買い物をしている人たちがすごく裕福そうに見えてしまって、いたたまれなかった。
けれど、せっかく来たのだからと、良さそうな色の服を選んでいざ試着。うーん、何か違うような。自分が大切にしたいイメージとちぐはぐになっているような。そんなことを思った。さらには、今の流行のデザインそのものが何か気に入らない。横幅が広めでゆったりしていて、というのがどうもしっくり来ない。
そう思う理由が試着を終えて元の服(ジャージ)に戻った自分の姿を鏡で見て分かった。何だ。もう十分かっこいいいからだ、と。
鏡の中のわたしは、ジャージを着ていて、黒く日焼けをしていて、体つきがヨガをやっているからか、ものすごくたくましくてしっかりとしていて、目はパッチリとしていて、研ぎ澄まされているような感じがしていた。何か目新しかったり、おしゃれなデザインだったり、高級な布地であったり、といった洋服などに頼る必要などはなかった。
要するに、自分の肉体というものがどんな高級な衣服にも最新の流行にも優っていたのだ。そのことに気付いて何だかほっとした。
最後にはその人がどう生きているかということ。それがかっこいいかどうかということなんだと思う。

変な人。
普通ではないと思う。
わたしが思っていることを言うとみんなひく。
そして、目の前にシャッターを下ろされて、
まさに閉店ガラガラ~。
わたしは気が付くと蚊帳の外。
なぜなら、今、大人気の
カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。
最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。
そう、なんか浮いてるの。
この世界、日本という社会から。
わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。
「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。
お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、
苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。
その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。
気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。
わたしはしゃべんないほうがいいと思う。
しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。
わたしが自分のことを語れば語るほど、
女の人はがっかりします。失望さえします。
でも、いいじゃないの。
普通じゃないのがわたしなんだから。
わたしは風になりたい。
風になってただ吹いていたい。
【属性】
男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。